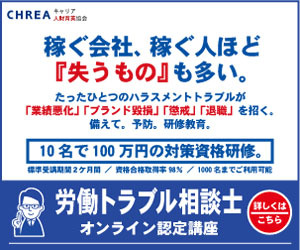「協調性」と「同調圧力」、「周囲と同じように行動する」というニュアンスを感じさせるよく似た言葉というイメージがある。
「協調性」はポジティブな意味で、「同調圧力」はネガティブな意味で使われそうだ。
まずは、それぞれの意味を調べた上で、いままでの経験上どのような場面にこれらの言葉が当てはまるか振り返ることにした。

1.「協調性」「同調圧力」の意味を調べてみた。
Wikipediaによると、「協調性(きょうちょうせい)」とは、
「異なった環境や立場にある複数の者が互いに助け合ったり譲り合ったりしながら同じ目標に向かって任務を遂行する素質」
とある。また、別サイトでは、その文字通り"協力して調和する力"を意味し、様々な価値観や考えを持つ人たちと折り合いをつけ、時に周囲を説得しながら、一つの目標に向かっていく力を指すと説明されている。
「協調性」を大きく分けると、「従順的な協調性」「主体的な協調性」の2パターンがある。「従順的な協調性」とは、周りの意見に従い空気を読んで調和していくことを指し、真面目さや誠実さなどが求められるケースが多い。「主体的な協調性」とは、自ら周りに働きかけ巻き込みながらゴールを目指すこと指し、「主体性」と言っても違和感がないイメージである。
「同調圧力(どうちょうあつりょく)」とは、
「地域共同体や職場などある特定のグループにおいて意思決定、合意形成を行う際に、少数意見を有する者に対して、暗黙のうちに多数意見に合わせるように強制・誘導することを指す。」
とある。
少数意見を有する者に対して多数意見を受容するよう迫る手段にはさまざまな方法がある。少数意見を有する者に対して物理的に危害を加える旨を通告するような明確な脅迫から、多数意見に逆らうことに恥の意識を持たせる、少数意見者が一部の変わり者であるとの印象操作をする、「一部の足並みの乱れが全体に迷惑をかける」と主張する、少数意見のデメリットを必要以上に誇張する、同調圧力をかけた集団から社会的排除を行うなどである。どちらかというと、やはり冒頭に述べた通りネガティブな印象だ。
2. 周囲に合わせて長時間労働に付き合うのは「協調性」ではない。「同調圧力」だ。
職場における代表的な事例が、長時間労働だ。効率的に仕事を進めており残業が少ない状況であっても、忙しい状況であってもこのように言う管理職を何人か見たことがある。
- 「○○は、残業が少ない。もう少し(残業してでも)サポートに回ってほしい。」
- 「みんな22時まで頑張っているのに、○○は22時まで頑張っていない。」
- 「他のメンバーの中には休日出勤している人もいる。もう少し、スケジュールに対する意識を持って対応してほしい。」
皆さんは、このような管理職がいかに未熟であるかお分かりいただけるだろうか?
残業することが当然の職場において、口には出さない、または遠回しに言うけれども、周囲と同じく残業することを強要するような雰囲気がある。このよう周囲と同じ行動を強いる雰囲気や威圧感こそが「同調圧力」である。
そもそも「残業」「休日出勤」は「当たり前」なのではなく「特例」なのだ。また、「残業」「休日出勤」は上司からの指示・命令で行うものである。上記のセリフはいかに「残業」「休日出勤」が当たり前になっており、管理職のマネジメントが未熟であるがゆえにブラックになっていると自ら言っているようなものだ。恥ずかしくないのだろうか?
o08usyu7231.hatenablog.com
o08usyu7231.hatenablog.com
本来、「残業が少ないから残業を多くしてほしい。」というスタンスではなく、業務配分を見直したり、負荷の平準化をはかるように調整することが、管理職のやるべきことである。マネジメントの未熟さや、組織として過大な要求を受けているがゆえ、そのしわ寄せが末端のメンバーに押し寄せているという状況を放置しているのは怠慢極まりない。
重要なことは、残業が少ない人のことを「協調性が欠けた人」というふうに言ってはいけないことである。「周囲と同じようにする」という、組織における「従順的な協調性」を重視しているように見えるのだが、むしろ「同調圧力」のイメージの方が強く、「早く退社しにくい職場」を暗黙のうちに作り上げてしまうことになる。有給休暇が取りにくい職場も同じだ。「同調圧力」を「協調性」と称して正当化し、職場のメンバーが迷惑を受けている典型的な事例だ。
3. 新型コロナウィルス対策における「ワクチンハラスメント」
「ワクチンハラスメント」、最近時々聞く言葉だ。新型コロナウィルスの感染拡大の対策としてワクチン接種が進捗している。当初は医療関係者や高齢者を優先して進められてきたが、徐々にそれ以外の人にも広まりつつある。「ワクチンハラスメント」とは、新型コロナウィルスのワクチン接種を強要することである。また、接種しない人に対して差別的な発言や行為もハラスメントに該当する。
未知のウィルスに対して開発されたワクチンなので、接種後の発熱、疲労、アナフィラキシー症状、接種部位の痛みなど副作用もあり、接種をためらっている人もいる。ニュースでも聞くように、副反応が多くの人に発生している状況、また2回接種完了(一部では3回目の接種を行うところもある)しても感染・発症してしまうケースもある。特に若い人への副反応が多く見られたり、中には悲惨なことに亡くなる方もおられるようだ。そのため、接種に対して慎重になるのも当然である。現時点日本においては接種は必須ではない。接種するかしないかは、各人の判断に任されている。私の職場においてもそのように通達があった。だから、職域接種において、「誰が受けた」「誰が受けていない」という話はしづらいし、そのような話が出ても「接種しないという選択肢もある」と私は理解している。
「ワクチンハラスメント」が起きる企業では、最初は接種をためらっていた人でも周囲に合わせて接種を受けるようになり(「同調圧力」)、接種を受けない人に対しての風当たりが強くなったり、「みんなが受けているのになぜ受けないのか?」といった「協調性欠けた人」として扱われ、次第に業務に影響が出るなど、普通では考えられないことが起きているそうだ。まさに、「同調圧力」と「協調性」をはき違えている事例であり、接種を受けない人へのハラスメントになる。
o08usyu7231.hatenablog.com
4.「協調性」は必要。「同調圧力」から抜け出そう。
「協調性」と「同調圧力」の違いを分かりやすく言うと、「協調性」とは自らの意思で協力し合うことを表すこと、「同調圧力」とは外部からの周囲に合わせることを強いる雰囲気である。
組織の中でやっていくためには、組織の規律を守り、他のメンバーと協力していくことが、社会人の基本と言える。しかし、先程の長時間労働の例にもあるように、組織の中でやっていくために必要な「協調性」というマインドを都合良く悪用した「同調圧力」が漂っている職場は注意と見極めが必要だ。
「組織の中で成長する」と言えば聞こえは良いが、それは「その組織レベル相応の成長しかできない」ということでもある。他に「同調圧力」の一例とも思えるのが、何か悪い評判があったときに「みんな言っている!」という一言である。「みんな」ってどの単位のみんななのか、「みんな」という数を持ち出して「同調圧力」をチラつかせ、相手を従えさせたいという言っている人にとって都合の良い手段である。このようなケースに限って、実際に言っている人が一部であったり、「数」のみを重視し「内容」「中身」を軽視していたりと、あまり信用できなかったりするものである。「みんな言っている!」と言われても冷静さを保ちたいものだ。
o08usyu7231.hatenablog.com
「同調圧力」は、「長時間労働」や「ブラック労働」が無くならない理由の1つでもある。誰か一人がおかしいと思っていても、なかなか声を挙げにくいものである。
この資格を取得するためには、認定講座を受講していただく必要があります。受講後の試験に合格した方が資格を取得できます。講座は全てオンラインで受講できます。資格の内容は、人事や労働に関する知識です。就職、労働条件、退職、残業、休職、解雇などの法律や決まり、トラブルに関する知識を得ることができます。
「ブラック企業対策のノウハウを知りたい」
高い成長意欲を持った優秀な人材が退職するのは、「長時間労働&同調圧力に巻き込まれる」→「心身疲弊」→「効率低下」→「更に長時間労働」という負のサイクルから抜け出し、健全・健康で、本来のパフォーマンスが発揮でき、成長できる環境を求めているという理由であることが少なくない。
冒頭にも記載したが、「主体性」も「協調性」の一部と捉え、「協調性」と称する「同調圧力」に影響されすぎないように冷静な見極めが必要だ。「同調圧力に屈しない」ことを「協調性が欠けている」と称するのは勘違いも甚だしい。あなたの職場やあなたが置かれた環境を冷静に見極め、生き生きと働くことができる職場で活躍してもらいたい。